個人再生の適用条件がわかる!自宅を残したい場合も解説

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額する救済制度です。
例えば、500万円の借金がある場合は、5分の1の100万円に減額することができますので、非常に大きな減額効果がある手続きです。
また、住宅ローンがある自宅を残すことができる特則(住宅資金特別条項の利用)もあり、借金を減らしたいが自宅は手放したくないという方にメリットがあります。
つまり、自己破産では自宅は手放すことになるため、引っ越しを余儀なくされてしまうのに対して、個人再生が認められれば、住宅ローン以外の債務を減らして、生活の負担を減らすと共に自宅を守ることもできるということです。
ただし、この個人再生を行うためには認められなくてはならず、だれでも行えるわけではありません。
大きな条件としては、以下の3つを満たす必要があるとされています。
① 継続した一定の収入が見込まれること
② 減額する債務は、個人の借金であること
③ 減額された債務を原則3年で返済する収入があること
本文にて細かく説明しますが、住宅ローンのみを残したい場合は住宅ローンの借り入れの条件が加わるため、自身が適用できるのか注意が必要です。
個人再生の条件をよく理解したうえで選べるように、今回は個人再生の条件について詳しく説明します。
個人再生の適用条件
では、個人再生の適用条件を一つずつ見ていきましょう。
個人再生の手続きは「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」と二つの種類がありますが、一般的に利用されているのは「小規模個人再生」の手続となるため、まずはこちらを確認していきます。
安定した継続的な収入があること
まず、安定した継続的な収入があることが最低限の条件です。
この安定した継続的という意味は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」とされており、例えば転職が既に決まっており、給与が減る予定であることや、仕事を失ってしまう状況では認められません。
例えばですが、派遣社員であり期間の満了が近いなど更新できない可能性があると判断されると、反復した収入があるとはならないとして、個人再生ができない場合があります。
もちろん、派遣社員の全てが認めらないわけではなく、非正規雇用でも再生計画の期間において継続的反復的な収入を得られる見込みがあるのであれば、小規模個人再生をすることができます。
個人の借金総額が5000万円以下であること
次に、個人の借金であり、総額が5000万円以下であることも条件です。
事業用の借金でなければ、問題はなく、この負債総額については、住宅のローンは含みません。
なお、最低弁済しないといけない金額は下記の通りです。
| 借金総額(基準債権額) | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 借金総額以上 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円以上 |
| 500万円超1500万円以下 | 借金総額の5分の1以上 |
| 1500万円超3000万円以下 | 300万円以上 |
| 3000万円超5000万円未満 | 借金総額の10分の1以上 |
最低弁済額は、表の通りですが、自身に退職金見込み額がある場合や、ローンを完済した家(またはアンダーローン)がある場合は注意しなくてはいけません。
「債務者は、個人再生の手続をしているときに所有している財産の総額(清算価値)を、債権者に最低限支払わなければならない」という考えに基づき、保有財産によっては「清算価値保証基準」によって算出された金額を最低弁済額として適用するケースも存在します。
例えば、借金額が300万円の場合は、最低弁済額は100万円です。
ですが所有する財産の清算価値が200万円であれば、清算価値が最低弁済額を超えるため、「清算価値保証基準」が採用されて、個人再生が出来ない可能性のほうが高いといえます。
個人再生によって減額された借金を原則3年で返済できる収入である
そして、再生計画認可が確定してから減額された借金を原則3年間、最大5年間で、借金を返済していくことになります。
利息がなくなり、個人再生で減額もしているため、最終的な返済総額は大幅に減りますが、返済期間が短くなるため、月々の負担が大きくなってしまう可能性があることは理解しておきましょう。
つまり、個人再生の返済期間は、その間借金を返し続けるだけの収入をきちんと確保し続けなくてはなりません。
借金の額と月々の支払い可能な金額の関係で、「支払不能、あるいはその恐れがあるといえる」と評価されてしまうと、個人再生は利用できないので、この場合は任意整理や自己破産を検討することとなります。
このように、無理な再生計画を組んでも、申立人の収支状況から支払いが現実的ではないと判断され、申し立てをしても裁判所は再生計画を認可できないのです。
過半数の債権者からの同意が必要である
次に、提出した再生計画案について債権者の過半数から同意が得られることも条件となります。
ただし、実際は債権者の不同意は滅多にみられず、仮に1社の不同意があっても、再生計画の認可に影響がないケースとされます。
これは、たった一人の債権者が反対している場合であっても、他の債権者の持っている債権額が総債権額の過半数であれば認められるからです。
債権者からの同意がなかった場合の個人再生
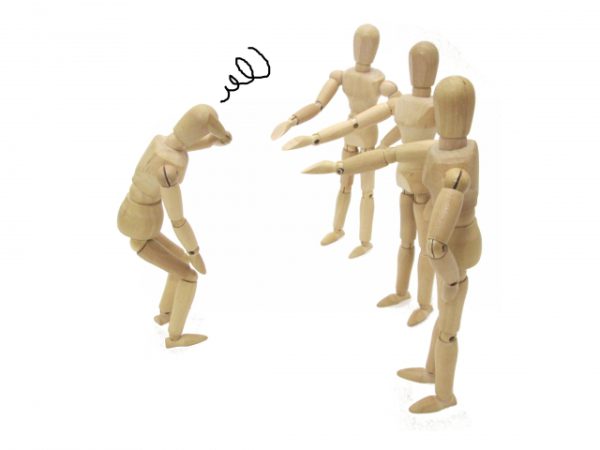
そこで、万が一、債権者からの同意がなかった場合の個人再生について説明します。
ここで、給与所得者再生という方法で考えることになります。
個人再生は、必ずしも債権者の同意が必要ではなく、同意がない場合も手続きを進めることができる方法もあるのということです。
給与所得者等再生を使うことを検討する
小規模個人再生が使えない場合は、給与所得者等再生を使うことを検討しましょう。
この給与所得者再生手続ではこのような多数決の条件は存在しないため、債権者の意向に関わらず手続を行うことができます。
※ちなみにですが、「半数以上の債権者が反対」というケースは、かなり珍しいケースとされているので心配しすぎないようにしましょう。
小規模個人再生の要件にプラスして厳しい条件がある
ただし、小規模個人再生の要件にプラスして、厳しい条件が加わります。
プラスの条件は下記の通りです。
① 給与変動の幅が年間20%以下であること
② 可処分所得の2年分以上の支払いが可能であること
③ 過去7年以内に、自己破産や給与所得者等再生を行っていないこと
まず、正社員のサラリーマンであっても、ボーナスや歩合などの要素が大きく、1年で20%以上収入が減ったり増えたりしていると、収入の変動の幅があるとして行うことができません。
また、可処分所得の2年分を基準として、最低返済額の条件に加えることが設けられています。
可処分所得とは、収入から税金を差し引いた手取り収入から、2年間可能な限りの節約生活をした場合に余る金額(生活最低費)のことをさします。
※最低生活費は、居住地域の自治体の生活保護基準を元に定められており、年齢や収入、家族構成などに応じて決まります。
そしてこの可処分所得の2年分を計算してみると、最低弁済額より高額になるケースが多いのです。
この条件が加わることで、最終的な返済額が小規模個人再生よりも増えてしまうことがあるため、基本的には小規模個人再生を使っており、給与所得者等再生を使うことは少ないということなのです。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するときの適用要件

では、続いて3章では住宅ローン特則を利用するときの適用条件をまとめます。
住宅ローンには通常、購入した不動産に担保として抵当権が設定されているため、原則的な考え方に則って取り扱えば自宅は個人再生手続きをした時点で手放さなければなりません。
しかしながら、住宅はその他の財産と違って生活の基盤になっているものであり、住宅の維持はその後の経済的な更生につながると考えられています。そのため、住宅ローン特則を利用することで、自宅を残して債務の整理ができる場合があります。
そもそもこの住宅ローン特則は、住宅が換価処分されたとしても、住宅ローン以外の債権者は影響を受けないことで成り立っています。
住宅ローンには抵当権が設定されているので、自宅を売却しても抵当権者(住宅ローンの借入先の金融機関)が優先して売却額を回収することになります。そのため、自宅を売っても他債権者へ住宅の売却額が配当されないのであれば、家を売っても意味がない、という理由で自宅を残すことが認められるのです。
ただし、このローン特則は、債権者平等の原則の例外となりますので、認めてもらうためには以下のような条件を満たす必要があります。
住宅ローン以外の債務を圧縮すれば十分に返済が可能であること
一つ目は、住宅ローン以外の債務を圧縮すれば十分に返済が可能であると判断されなくてはいけません。
この住宅ローン特則を利用しても、住宅ローン自体は減額の対象に含まれないため、これまでどおりの額を毎月支払わなくてはなりません。
個人再生後の最低弁済額の支払いと、住宅ローンの支払いが問題なく行えると判断されることが条件となります。
オーバーローンであること
二つ目は、オーバーローンであることが条件とされています。つまり、「住宅ローンの残高>家の評価額」の状態にあり、家を売っても住宅ローンの全額返済ができない状態でなければなりません。
この要件は、先述した、すべての債権者を平等に扱うという考え方から、住宅の売却額から住宅ローン残高を引いて差額が出る場合、その差額は「清算価値」となり、清算価値があがると、その分はプラスして返済しなくてはいけないとしています。
例えば、住宅ローンの残債が2000万円で、家の価値が2500万円の場合は、清算価値が500万円であることになります。
この場合は、個人再生で減額され100万円の借金返済であったとしても、返済額は減額された100万円ではなく、清算価値の500万円になります。
つまり、ローン完済済み(あるいはアンダーローン)の自宅がある場合などでは、清算価値が100万円を超えるどころから、負債額を超えてしまう場合も珍しくありません。
負債額を超える場合には債務超過にならず、個人再生の申し立てはできないということです。
住宅ローンの滞納がないこと

そして、三つ目として住宅ローンの滞納がないこともポイントになります。
少し遅れた程度では、遅れた分を支払うことで問題はありませんが、住宅ローンを一定期間滞納していると、住宅ローンの「期限の利益」を喪失し、債権は保証会社へ代位弁済されます。
このような代位弁済がなされた場合には、原則として住宅ローン特則の利用はできません。
例外的に、保証会社による代位弁済から6か月が経過する前に、個人再生手続開始の申立てをすれば、住宅ローン特則を利用することができとされていますが、もちろんのこと滞納額のすべてを債権者に支払う必要があります。
不動産に他債務の抵当権がないこと
四つ目は、不動産に他債務の抵当権がないことも条件となります。
住宅を担保として、住宅の建設・購入・改良以外の目的(他のローンの返済など)借入をしている場合などには、住宅ローン特則を利用することはできなくなります。
例えば、不動産担保ローンや太陽光ローン、前の家の残ったローンの上乗せ分などがある場合には、住宅ローン特則は利用できません。
借り換えローンが不動産担保ローンではないこと
五つ目は、個人再生の申し立て前に、住宅ローンの借り換えをしているのであれば注意が必要です。
借入れ使途理由が「住宅ローン」になっていないケースがあるからです。
四つ目に該当する理由と繋がりますが、たとえば、事業用の借入れのために不動産担保ローンを組んだという場合には、住宅ローン特則を適用することはできません。
例えば、以前の家から今の家に買い替える際に、前の家のローン残債を今の家のローンに上乗せして組んだ場合などに、借り入れ用途が違うことがあります。
この借換え後の住宅ローンが、住宅資金貸付債権(民事再生法196条3号)に該当していれば、個人再生手続きで住宅ローン特則を利用することができるため、 借り換え時に、金額の使途を明らかにする資料を残しておくことは必要なのです。
自身が引き続き居住すること
六つ目に、自身が引き続き居住することも条件となります。
債務者(再生申立人)の居住用として使用されている建物であることが必要であり、たとえば、事業用・投資用の不動産など、居住の実態がないものは対象外となります。
債務者がその居住地にいることが再生計画としてよいとされるという倫理に沿った考え方であるためにこの要件は満たしていなくてはいけません。
個人再生が向いているのかを検討しておく
最後に、個人再生を行う前に、個人再生が向いているのかを検討しておく必要はあります。
返済を大幅に縮減できるとはいえ、最低でも100万円を3年間で返済しなければなりません。
資産の額が(保険の解約返戻金や、現時点での退職金見込み額を含む)が100万円以上あったり、負債総額が500万円以上であると、毎月の返済額は増えます。
毎月確実に返済できる必要があり、仮に1000万円の負債総額を個人再生で減額し200万円となっても、3年分割で払うことを想定すると、毎月5.5万円の返済と、住宅ローンの約定どおりの返済見込みがなければ、再生計画が認められません。
適用要件に当てはまらない場合は他の債務整理を検討する
そのため、個人再生の適用要件に当てはまらない場合は他債務整理の方法を検討しましょう。
個人再生は、住宅ローン特則を利用することで住宅ローンを継続できるという最大のメリットはあります。
しかし、たとえば、多額の返戻金がある保険を保有している場合や、不動産の清算価値が高すぎる場合などは、換価して工面する方法や、任意整理を行うなどで、他の解決策を考えた方が良いでしょう。
また、債務が思ったより高額になり、個人再生での返済期間では余計に毎月の返済が苦しいと想定されたときは、自己破産も検討すべき段階になります。
まとめ
今回は、個人再生の条件を詳しく説明いたしました。
住宅ローン特則を利用するとなると、さらに多くの要件があるため、自身が個人再生の適用になるか不安な方は専門家への確認をしてください。
もちろん、個人再生は自宅を残せるという大きなメリットがありますが、自身の財産や職業などによっては、他の債務整理を選択することで負担が軽くなることもあります。
また、資産を換価することで、早期の再生に向けて状況は変わりますので、総合的に判断ができるように、資産となる不動産や、加入している保険の確認も行っておきましょう。